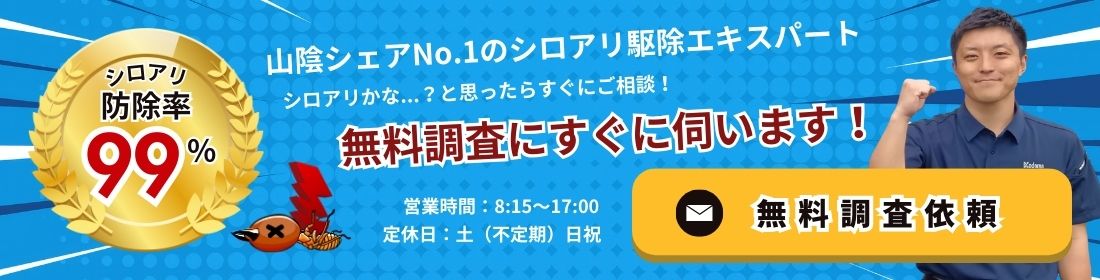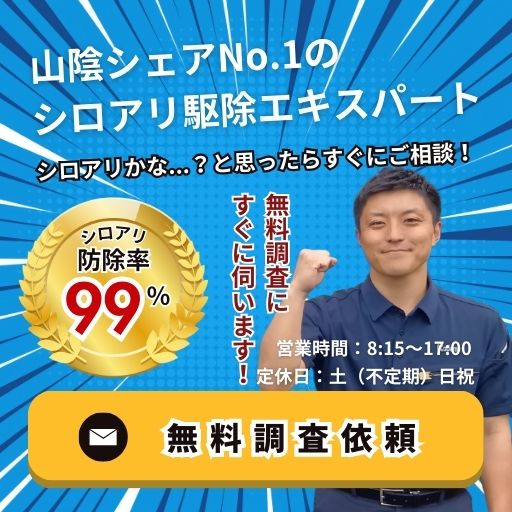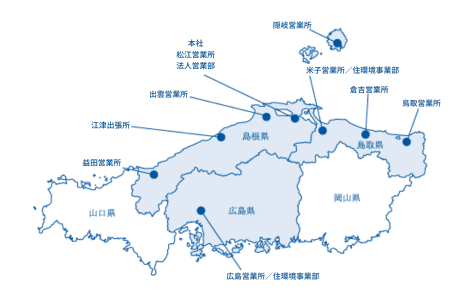
ブログ
-

No.11 人文虫学(私的分類学) ~人と虫との関わり学 (8) ~
自然を全身で感じた人 野外で過ごすと食事が美味しいのを経験したことがありますか?空腹が調味料になっているだけとは思えません。自然界には不思議なエネルギーが宿っているようにも感じます。 いつの時代でも自然を愛する人は多いのですが、この世にあ... -

No.10 人文虫学(私的分類学) ~人と虫との関わり学 (7) ~
確かな社会とは 1997年、バブルが崩壊し、アジアの工業先進国であったタイがIMF(国際通貨基金)の管理下におかれたとき、プミポン国王が国民に呼びかけた言葉があります。 その主旨です。 「工業先進国をやめよう。国が栄えて社会が滅んでは意味がない。国... -

No.9 人文虫学(私的分類学) ~人と虫との関わり学 (6) ~
現代文明も自然の一部 虫はおろか草一本、ゼロから創り出すことは出来ない人類。 この事実は、「私達の存続は、地球上の動・植物を含む生物系の食糧や鉱物系の資源を利用することだけによって許されていること」を暗示します。言い換えれば、宇宙や地球を含... -

No.8 人文虫学(私的分類学) ~人と虫との関わり学 (5) ~
科学と経済の幻想 科学技術を基盤とした現代の経済社会は、確かに人々の生活を豊かにする素質を備えています。しかし一方で、一度この経済社会に足を踏み入れてしまうと、それが全てであるかのような錯覚を人々に抱かせ支配する作用も備えています。そうし... -

No.7 人文虫学(私的分類学) ~人と虫との関わり学 (4) ~
経済社会の柵 仏教の世界を除けば、最近になってようやく、人間は生物の多様性によって生かされていることを悟るようになってきました。 一方、今日の文明社会と呼ばれる地域都市では、ほとんど自然との接触なしに人間が生涯を送ることができるという、幻... -

No.6 ~9月から10月は、スズメバチの季節~ スズメバチは凶暴か?
スズメバチは凶暴か? この質問に対しては、「巣を守ることには勇敢で、それ以外は凶暴になる暇がない」と言うのが正しいようです。毎年、秋になるとスズメバチに刺される事故が報じられますが、不用意に巣に近づいたことに因るものです。餌を求めて飛んでい... -

No.5 ~9月から10月は、スズメバチの季節~
スズメバチの季節 9月から10月にかけては、スズメバチの活動が一番盛んになる季節です。 では、なぜでしょう? それは、ハチの仕事にとって仕上げの時期であり、個体数が最も多くなる時期だからです。 では、彼らの仕事の目的は何でしょう?それは、女王... -

No.4 人文虫学(私的分類学) ~人と虫との関わり学 (3) ~
虫の音を愛でる文化 虫を栄養源の一つとしてきた人間も、いつか虫の音(ね)に耳を傾け、詩歌を吟ずるまでの情緒的な文化を形成するようになりました。 虫の音を愛でる理由には、単純に音色による以外に季節感や雰囲気を感じる感性、小さく短命な生き物を... -

No.3 人文虫学(私的分類学) ~人と虫との関わり学 (2) ~
人間の文化と虫の関係 人間にとって虫との自然な関係は、「食べる」「見る」「聴く」ことにあると思われます。「迷惑する」「怖がる」などは、むしろ後発的で不自然な関係でしょう。人は虫を食べて命をはぐくみ、虫の姿を見て遊び、虫の音を愛でて情緒を養... -

No.2 人文虫学(私的分類学) ~人と虫との関わり学(1)~
日本文学と虫 古来、日本文学では、情景の描写に花鳥風月と並んで「虫」が登場したものです。紫式部、清少納言、志賀直哉の作品にも日常風景の描写に「虫」が織り込まれています。しかし、現代にちかづくほど情景は風景へと変わり、構造物へと視点が変わり...