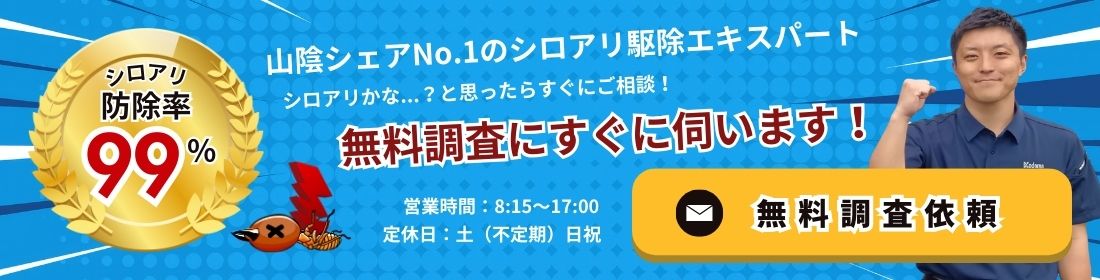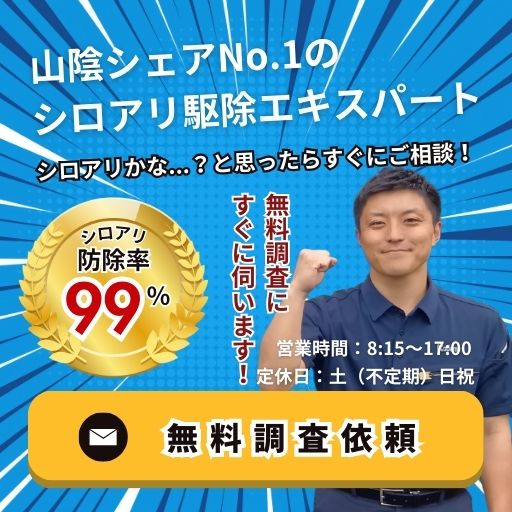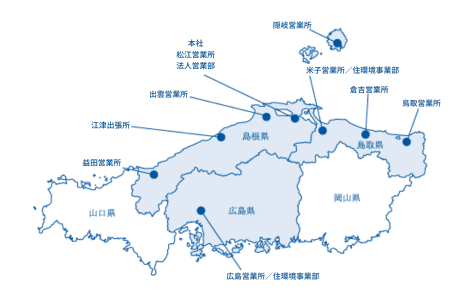
ブログ
-

人文虫学②(私的分類学) ―人と虫との関わり学―
食べて遊んで愛しむ コダマ虫太郎 前号は、「虫屋」を自認する人たちの文学と、虫と文化の関係に触れました。 虫を食べること 虫が嫌いな人は否定的かも知れません、しかし今でも世界の各地でご馳走として虫が扱われている習慣がある以上、農耕文化以前は... -

人文虫学①(私的分類学) ―人と虫との関わり学―
文化を育んだ虫 コダマ虫太郎 日本文学と虫 古来、日本の文学では、情景の描写に花鳥風月と並んで「虫」が登場したものです。紫式部、清少納言、志賀直哉の作品にも日常風景の描写に「虫」が織り込まれています。 しかし、現代に近づくほど、情景は風景へと変... -

虫の文化史 ⑰(虫偏のムシ) ―人と虫が奏でる文化―
「蛸(タコ)」の話 コダマ虫太郎 「蛸」はテコから タコを漢字で書くと、虫偏に、肖(しょう)と書きます。英語の「オクトパス」は、もともとラテン語で、「八本足」のことです。日本名の「タコ」は、新井白石によると、タコの「タ」は「手」で、「コ」は... -

虫の文化史 ⑯(虫偏のムシ) ―人と虫が奏でる文化―
「蛙(カエル)」の話 コダマ虫太郎 「カエル」の意味 カエルは漢字で書くと「蛙」。虫偏(へん)に土を二つ書きます。これを中国では、「あ」と発音します。英語の「フロッグ」は、ドイツ語の「フロッシュ」の流用で、喉を鳴らす意味です。いずれも、鳴き... -

虫の文化史 ⑮(虫偏のムシ) ―人と虫が奏でる文化―
コオロギの話 コダマ虫太郎 コオロギの音 身近な野の虫「コオロギ」ですが、日本だけではなく世界的にポピュラーな山野の虫です。彼らは、作物を食べる害虫ですが、綺麗な声と、闘争心から、人間に愛玩された虫です。ちなみに、コオロギはその昔「キリギリ... -

虫の文化史 ⑭(虫偏のムシ) ―人と虫が奏でる文化―
日本人とトンボ コダマ虫太郎 昔から日本人は、何かと「トンボ」を意識してきたようです。他の国と比べると、日本とトンボとの関係は半端ではありません。結論から言えば、「トンボは日本を代表する虫」といえます。 トンボの国 日本の別名を、「秋津島」... -

虫の文化史 ⑬(虫偏のムシ) ―人と虫が奏でる文化―
「ゴキブリ」の話 コダマ虫太郎 名前の由来と変遷 お馴染みの「ゴキブリ」ですが、その名前の由来は、「五器かぶり」から来ています。 五器とは蓋(ふた)のついた食器。「かぶり」はかじる意味です。つまり、「食器かじり」です。「ゴキブリ」というと今... -

虫の文化史 ⑫(虫偏のムシ) ―人と虫が奏でる文化―
「蚤(のみ)」の歴史 コダマ虫太郎 人間と付き合いの深い虫の歴史を眺めてみましょう。 かつて日本は「ノミ天国」 蚤は、世界中に約二〇〇〇種類ほどいます。そして、ずっと昔から人間を悩ませながら、それでも人と暮らして来ました。衛生状態の良い社会... -

虫の文化史 ⑪(虫偏のムシ) ―人と虫が奏でる文化―
「蛇(へび」の話 コダマ虫太郎 蛇が天敵の方も多いでしょう。しかし、怖いもの見たさから、興味は人一倍。直接遭遇は御免だが、高みの見物は大好きという人も、きっと多いはずです。 「蛇」の名前 ヘビは漢字で書くと、虫偏に、ウ冠(かんむり)の下に「... -

虫の文化史 ⑩(虫偏のムシ) ―人と虫が奏でる文化―
腹の虫」について コダマ虫太郎 「腹の虫」とは? お腹にわく寄生虫のことです。日本ではいま、「腹の虫」は絶滅寸前で、忘れかけられています。なので、まず予備知識として、代表的な三種類の「腹の虫」を、おさらいです。大きい順に言うと、サナダムシ、...