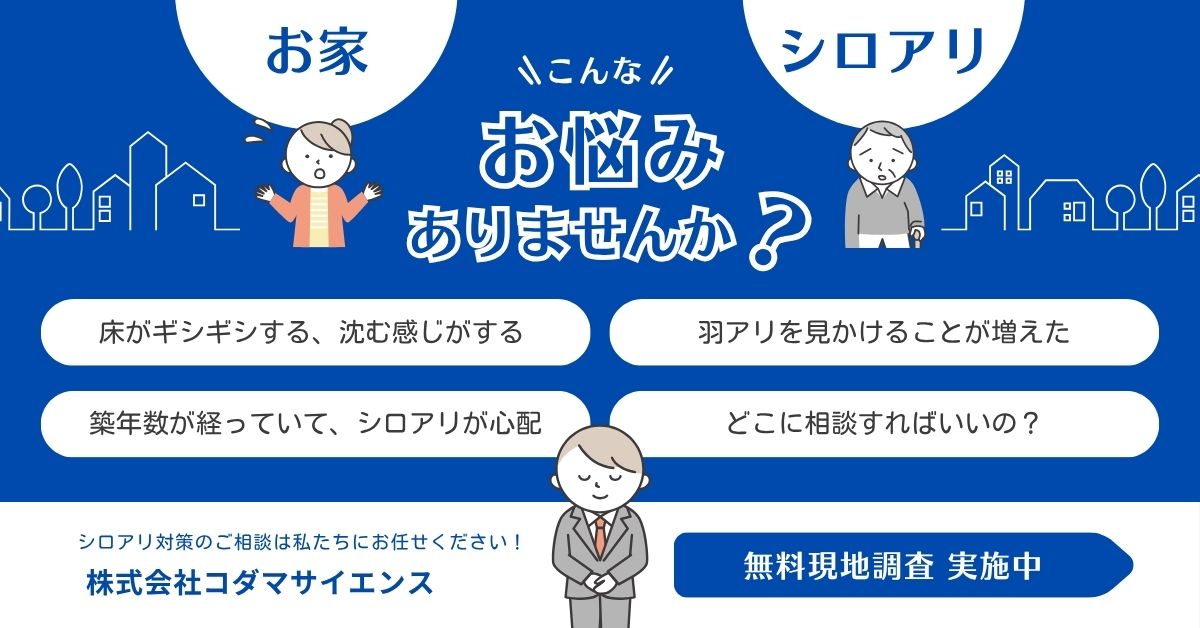文化を育んだ虫
コダマ虫太郎
日本文学と虫
古来、日本の文学では、情景の描写に花鳥風月と並んで「虫」が登場したものです。紫式部、清少納言、志賀直哉の作品にも日常風景の描写に「虫」が織り込まれています。
しかし、現代に近づくほど、情景は風景へと変わり、構造物へと視点が変わります。現代の私たちは、どうやら人間が創り出した物に心を奪われ過ぎているようです。
虫を愛した人たち
虫好きの人は自分を「虫屋」と称します。 虫屋としては、手塚治虫(漫画家)、北杜夫(作家)、養老孟司(解剖学者)、奥本大三郎(仏文学者)などが知られていますが、その虫好きは半端ではなく、手塚治虫さんは「オサムシ」をペンネームにし、奥本さんは近頃ライフワークの「ファーブル昆虫記」を出版したほどです。虫屋の虫好きは、「理由がない」問雨天で共通ですが、その根源的な理由については、後ほど触れてゆくことことにしましょう。
小泉八雲と虫
小泉八雲(ラフカディオ・ハーン) は、「怪談」や「耳なし芳一」で知られる、明治の帰化外国人です。彼の虫好きは徹底していて、著作が多いことはもちろん、松江(島根県松江市)の自宅の庭にムシを放して、鳴き音を楽しみました。 現存する愛用の煙管(きせる)百本のほとんどに虫の絵が入っていることからも、八雲の虫への傾倒ぶりが伺えます。東大の講義では、「本当に虫を愛する人種は日本人と古代ギリシャ人だけ」と述べています。ちなみに、著書「KUWAIDAN」(怪談)のつづりが変なのは、ハーンの妻、節(セツ)の出雲訛りで、「クワイダン」の発音によるものです。

「ゼフィルス」 手塚治虫
手塚治虫の作品に、少年時代の思い出を綴った「ゼフィルス」(シジミ蝶)という作品があります。終りの一節です。「空襲の炎が夜空を焦がした。一夜明けて山に登った僕の目に、無残に焦げたあのウラジロのいた森の跡が見えた…。僕は大声を上げて泣いた。
あれから三十数年、僕の村は変わった。今はモダンな住宅が立ち並び、戦争の悲惨さは残っていない。だがあの緑豊かなウラジロの森もすっかり消えてしまった。」
皆さん。少年の頃に戻って虫や自然とのかかわりを見直して見ませんか?
人間の文化と虫の関係
人間にとって虫との自然な関係は、「食べる」、「見る」、「聴く」ことにあると思われます。「迷惑する」、「怖がる」などは、むしろ後発的で不自然な関係です。人は虫を食べて命をはぐくみ、虫の姿を見て遊び、虫の音を愛でて情緒を養い世代をつないで来たとも言えるのです。
禅僧の良寛和尚も、蚤やシラミと仲良く暮らしていたようで、「蚤、シラミ音(ね)の鳴く秋の虫ならば、わが懐(ふところ)は武蔵野の原」、と詠んでいます。蚤のいる自分の懐を武蔵野に見立てたのには、恐れ入ります。
農耕文化という一品種多量生産で、特定の虫が大量発生するようになって、また、ごく僅かの種類の虫が疫病の媒介に関与することが解明されて、文明社会は、過剰なまでに虫を敬遠するとともに、文化(心)も経済という商品交換権の獲得競争に飲み込まれてゆくことになります。
次号では、「食べたり、遊んだり、音を愛でる」虫の文化についてご紹介します。
つづく